| 年月日 | 2011年1月29日 |
|---|
産経新聞 書評倶楽部に野口の書評が掲載されました。
ぜひ、ご覧ください。
角川書店 「鋼鉄の叫び」 鈴木光司著
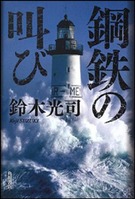
■共同体離脱の人間の拠り所
ひとりの人間が拠(よ)って立つ基盤とは何か。ひとつには、家族や学校、職場、地域社会、国家など共同体があげられると思う。人は一人では生きていけない。何かしらの共同体への所属や関わりの中で生きていくことのできる社会的な存在である。
日本人は、集団からはじき出されることを極端に恐れるという特性を持っている。要するに「村八分」に対する恐怖である。ゆえに、個人が疑問や異論を抱いて も、集団が醸し出す見えない鎖のような雰囲気が無言のプレッシャーを与え、「その場の空気」に従うことを余儀なくされる。
このような「集団と個人の力学」について本書は「特攻隊の編隊を自らの意思で離れ、生還した人間」である峰岸泰三中尉という人物にスポットをあて多角的に迫っている。
舞台はふたつある。ひとつは、1994年、バブル崩壊後の東京である。テレビ局で働くディレクターの雪島忠信は、戦後50周年特別番組の企画として「特攻 隊の編隊を自らの意思で離れ、生還した人間」にスポットをあてた番組を提案するべく、該当する人間を探し始め、奔走する。
もうひとつの舞台は、1945年、太平洋戦争の末期、場所は、鹿児島県鹿屋である。自ら志願して飛行機乗りになった峰岸中尉は、特攻隊員として、鹿屋を飛び立つ。しかし、いざという際に、彼は自らの意思で、生還するための選択をとる。
なぜ彼はそのような決断を下したのか。雪島が峰岸を探す過程で、うす皮を剥ぐように、峰岸の葛藤、その後の人生、そして思想が徐々に明らかにされていく。
雪島は企画を会議に通すことに成功するが、最終的には、プライベートでのあるトラブルからテレビ局を辞すことを余儀なくされる。つまり、拠って立つ基盤を 失うことになるのだ。しかし、峰岸の生き方、思想に勇気を得、葛藤の末、「何をしても食っていけるという自信」を抱く。
共同体から離脱した人間は、何を拠り所に生きていくことができるのか。本書は、こうした極めて普遍的かつ日本的な問いに対して、ひとつの
答えを提示している。